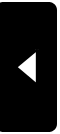2014年08月10日
統営散策-三道水軍統制営-11
つづき
その後、私たちが向かったのは、史跡第402号の 「統営三道水軍統制営」。
三道(慶尚道・全羅道・忠清道)水軍統制営は1604年に設営され、1895年に閉営されるまでの290年間、倭寇の進入に防備する朝鮮水軍の総本部だった。現在でいう海軍司令部。文禄・慶長の役の際、初代の水軍統制使(指揮官)に任命された李舜臣(イ・スンシン)が閑山島(ハンサンド)に設置した本部が最初の統制営だった。1998年2月に史跡に指定され、破壊された建物の復元計画に沿って、洗兵館(国宝第305号)や官庁施設、12工房などが復元された。
「統営三道水軍統制営」 の入口へ向かう通路には、「統営文化洞ポクス」 という石像が建っていた(▼)。村を伝染病や災いから守るため、1906年に作られたものだそう。東南は凶方位だという風水地理説により、洗兵館の入口であるこの場所が選ばれたとのこと。高さ198cm、外周160cm。

入口への通路には 「統制使以下皆下馬碑」(復元)も(▼)。

入口で入場料(3,000w)を払って入る。
最初に見えるのは望日楼(▼)。1611年、第10代統制使が建て、その後焼失した門を1769年、第128代統制使が建てなおした。別名 「洗兵門」 とも呼ばれ、通行禁止と解除を知らせる巨大な鐘があり、鐘楼とも呼ばれた。再び焼失したものを2000年に再建した。

望日楼をくぐると右手に 「受降楼」 と 「左庁」、左手には 「山城庁」。
受降楼は2階建ての楼閣で、統営城の南門の外に位置していた。文禄・慶長の役での戦勝を記念し、1677年第58代統制使が建てた。海岸の埋め立てにより船着場の本来の姿が失われ、1986年、現在の位置に移転、再建された(▼)。

受降楼を正面から見たところ(▼)。

左庁は軍官と兵士が控室として使った建物で、待変左庁とも呼ばれる(▼)。

山城庁は統営城を守る山城中軍などが勤務した場所(▼)。1708年に第83代統制使が建てたがその後焼失、発掘遺構や文献をもとに最近、再建された。

山城庁の内部には、統合三道水軍統制営の全景の模型が展示してあった。

そして望日楼をくぐって正面には階段と 「止戈門」(▼)。門の向こうに見えている巨大な屋根は洗兵館のもの。

つづく
その後、私たちが向かったのは、史跡第402号の 「統営三道水軍統制営」。
三道(慶尚道・全羅道・忠清道)水軍統制営は1604年に設営され、1895年に閉営されるまでの290年間、倭寇の進入に防備する朝鮮水軍の総本部だった。現在でいう海軍司令部。文禄・慶長の役の際、初代の水軍統制使(指揮官)に任命された李舜臣(イ・スンシン)が閑山島(ハンサンド)に設置した本部が最初の統制営だった。1998年2月に史跡に指定され、破壊された建物の復元計画に沿って、洗兵館(国宝第305号)や官庁施設、12工房などが復元された。
「統営三道水軍統制営」 の入口へ向かう通路には、「統営文化洞ポクス」 という石像が建っていた(▼)。村を伝染病や災いから守るため、1906年に作られたものだそう。東南は凶方位だという風水地理説により、洗兵館の入口であるこの場所が選ばれたとのこと。高さ198cm、外周160cm。
入口への通路には 「統制使以下皆下馬碑」(復元)も(▼)。
入口で入場料(3,000w)を払って入る。
最初に見えるのは望日楼(▼)。1611年、第10代統制使が建て、その後焼失した門を1769年、第128代統制使が建てなおした。別名 「洗兵門」 とも呼ばれ、通行禁止と解除を知らせる巨大な鐘があり、鐘楼とも呼ばれた。再び焼失したものを2000年に再建した。
望日楼をくぐると右手に 「受降楼」 と 「左庁」、左手には 「山城庁」。
受降楼は2階建ての楼閣で、統営城の南門の外に位置していた。文禄・慶長の役での戦勝を記念し、1677年第58代統制使が建てた。海岸の埋め立てにより船着場の本来の姿が失われ、1986年、現在の位置に移転、再建された(▼)。
受降楼を正面から見たところ(▼)。
左庁は軍官と兵士が控室として使った建物で、待変左庁とも呼ばれる(▼)。
山城庁は統営城を守る山城中軍などが勤務した場所(▼)。1708年に第83代統制使が建てたがその後焼失、発掘遺構や文献をもとに最近、再建された。
山城庁の内部には、統合三道水軍統制営の全景の模型が展示してあった。
そして望日楼をくぐって正面には階段と 「止戈門」(▼)。門の向こうに見えている巨大な屋根は洗兵館のもの。
つづく
Posted by dilbelau2 at 08:00│Comments(0)
│統営